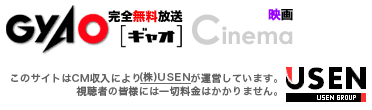2006年04月11日(火)
|
バリカム 撮影技術でアクセスがあった。 検索されたページは会社の日記「日々好日」のアーカイブだった。XMLには対応していないただのHTMLだがよく検索される。すでにバリカムでのハイビジョン撮影の現場はホームページのShootingにアップしているが、昨日一日で30ほどのページビューがあった。いかにハイビジョンに対する関心が高まっているかを示している。ちなみにHDV方式ハイビジョンカムコーダーを紹介したページは単独で991アクセスあった。そして今月10までのアクセスはすでに406アクセスになっている。おそらく月末には1200〜1300になるだろう。やはり世の中は確実にハイビジョン化してきているようだ。 今日の番組でパソコンとテレビの融合をテーマにしていたが、さてどうだろう。私が考えるに、30〜40インチクラスの大型テレビはパソコンとはなじみにくいのではないかと思う。パーソナルコンピューターゆえにテレビもパーソナルであるべきだ。画面から40〜50cmの距離を置いて操作するパソコンと数メートルの距離を置く大型モニターでは同居は難しいだろう。先日息子が新しく購入した大型液晶テレビにパソコンを繋いだというので見せてもらいに行ったが、どうも違和感があった。ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスで一見快適に思えるが、画面との距離は気持ちが悪い。セミナーのパワーポイントを見ているわけではないから、やはり文字は近くで読みたい。モニターは手が届く距離に置きたいのだ。 逆に私が使っている17インチのハイビジョンモニターのWOOOは1280×768の解像度でパソコンを表示でき、パソコン表示状態でもテレビをピクチャーインピクチャーで見ることが出来る。J:COMで見る地上波デジタルやBS、CATVのハイビジョンはPinP表示では6インチ程度の子画面として表示されるが、さすがにハイビジョンだけあって小さな文字まで高精細に見ることが出来る。SD放送の画質とは段違いだ。パソコンを使いながら子画面のテレビを楽しめるということも融合のスタイルである。もちろんパソコンを使わない場合はパーソナルテレビとしてSD〜HDまでを受信でき、その上D4端子でハイビジョンVTRのモニターになる。視聴距離はパソコンと同じ40〜50cmで視野角は60度ほどだ。ハイビジョンの場合は近づいてもボケていないから一人で楽しむには一応大迫力と言える。 ではリビングに置く大型モニターはどうだろうか。家族で見るにはワイド40インチは最適なサイズだ。もしこのモニターにパソコンが組み込まれていたらはたして便利だろうか?みんなで見ていると時にメールが来たり、誰かがパソコンを使いたくなったり・・・ 大型テレビはまさにエンターテインメントテレビである。エンターテインメントにパーソナルは余分ではないだろうか。そして大型液晶やプラズマテレビは価格を考えると最低でも6年は使うことになる。しかしパソコンはどうだろう。第一線で使えるのはせいぜい2〜3年、長くても4年程度だ。ソニーやNEC他の家電メーカーのパソコンは四季の移り変わりに合わせて新モデルを発表し、処理速度も半年毎に高速化している。みなさんも経験されていると思うが、FMやCDは聞けるのにカセットが駄目になったCDラジカセ。DVDは調子が良いのに、VHSが壊れたコンパチビデオデッキ。やはり寿命の異なるものを融合させると短いものが足を引きずることになる。 大型テレビはやはりテレビ受像機であるべきだと思う。しかしネットワークへの接続は出来る方が良い。双方向番組が今後増えることになるし、紅白のような視聴者参加は面白い。また災害時に備えインターネットと連動した情報表示なども必要だろう。そして気に入った画面をキャプチャーしたり、ハードディスクへの録画や、DVDへの書き出はオンボードで出来るとよいだろう。内臓一体型ならリモコンも一つで済む。あくまで大型テレビは家族のエンターテインメントであるべきだ。使いやすさが重要になる。 余談だがJ:COMのSTBのブラウザボタンをご存知だろうか。J:COMデジタルしか繋いでいなくてもこのブラウザボタンでWEBを閲覧出来るようになっているのだ。しかし画面は640×480のため殆ど実用にならないが、確かにSTBにはケーブルモデムが繋がっていて、インターネットに接続できる。現在はJ:COMはペイパービューの課金やオンデマンド放送、ソフトウエアの自動アップデートに利用しているだけのようだが、今後新しいアプリケーションが追加されるのではと微かな期待を持っている。自動アップデートは一日数回アクセスがあり、モデムの電源が入った状態でSTBの電源を切っておけば深夜などに実行されるようになっている。念のために言っておくが、私はペイパービューは利用していない。 「バリカム 撮影技術」からとんでもない方向へ進んでしまったが、総務省が進めるハイビジョンの一般化と大型ハイビジョンテレビの普及は加速度を得ながら進んでいると考えるこの頃である。 |
2006年04月10日(月)
|
HDVの今後というキーワードだ。 日本ビクターから始まったハイビジョンフォーマットのHDVだが、今はソニーやキヤノンもハイビジョンカムコーダーを展開している。特にソニーでは家庭用ハイビジョンから業務用まで展開している。当初発売されたHDR-FX1は業務用に発展しHVR-Z1Jとして進化した。これは私の会社でも大変気に入って使用しているキャメラだ。その後CMOSを使ったHDR-HC1が「身近になったハイビジョン」というキャッチフレーズで発売された。これもすぐに業務用のHVR-A1Jに発展した。そして現在家庭用は今「手のひらサイズのハイビジョン」としてHDR-HC3になった。 さて、今後のHDVだがどうなるのだろうか。かってベーターで大きな痛手を負ったソニー(実際には放送用ベーターカムに発展し、今なおそのフォーマットはハイビジョンのHDCAMまで引き継がれている)は再び8ミリビデオのテープを使用するデジタルエイトで痛手を負った。ただしデジタルエイトでは普及率も低かったために大きな痛手ではなかった。かなり昔だが、オーディオカセットを大きくし、オープンリールテープを収めたエルカセット(ELカセット)を日立、TEACなどとともに発売したが、今では幻のフォーマットとなってしまった。 様々なフォーマットを世に送り出したソニーだがDVは違った。松下もビクターも、シャープもDVでは皆共通している。家電メーカーが万人に共通のフォーマットを提供することは素晴らしいことだ。DVカセットを使ったハイビジョンフォーマットのHDVはまさに科学技術の財産と言えるだろう。AudioCD然り、DVD-Video然りである。要は互換性である。 最近ソニーでは光磁気ディスクを使用したXDCAMやXDCAM HDをすでに発売し、価格もHDCAMに比べると半額以下ということで大きな注目を集めている。今後の展開いかにというところだが、現状ではHDVが万人共通のフォーマットという地位を築いている。DVフォーマットにおいて松下はminiDVのSDみであり、HDはP2メディアということになる。確かに優れた記録メディアだが、半導体メモリーということでコストがかかる。また業務用テープメディアは蒸着テープを使ったDVやDVCAMとは異なり、塗布式のDVCPROになる。DVと同じ25MbpsのDVCPRO 25の他に放送用として4:2:2サンプリングで50MbpsのDVCPRO-50や100MbpsハイビジョンのDVCPRO HDは独自のフォーマットだ。実際にはオリンピックなどでも使用されているが、やはりソニーのベーター系は大きな壁になっている。最近は松下もソニーと操作性をそろえることでキャメラマンには歓迎されるようになった。しかし問題はアーカイブスとの互換性ということだろう。放送局やプロダクションにはベーターカムで撮影された膨大な映像資産がある。ソニーのHDCAM VTRはハイビジョンのHDCAMだけではなく、BETACAMテープを使ったアナログベーカム、デジタルベーカム、ベーターカムSX等をすべて同じHDCAM VTRで再生できるという強みがある。 同様のことがHDVで起こっている。HDV方式の新しい業務用VTRが発売されるが、この新製品はHDVのみならず、DVやDVCAMのラージカセットまで再生できる。もちろんHDVのラージカセットも再生可能だ。互換性が重視されたことで業界への浸透はスムーズにゆくだろう。こういうことを考えれば「HDVの今後」ということでは大きな不安はない。 今後いかにHDVを万人共通のメディアにするかは、どういったメディアにHD映像を残すかということだ。HD-DVDが先日発売されたが、ブルーレイ陣営がその後を追うように発売を予告した。フォーマットの2極化は決してユーザーに好都合とはいえない。出来れば同じフォーマット上で技術を競ってもらいたいとは思う。しかしこれまでの放送用VTRの進化を考えると、異なったフォーマットが存在しても技術的には大きな進歩が期待できる。そして競った結果優れたものがだけが残ることになるだろう。 |
2006年04月08日(土)
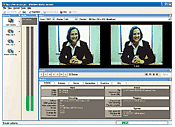 「ビデオ エンコーディング 料金」での検索だ。 「ビデオ エンコーディング 料金」での検索だ。検索でヒットしたページや会社概要、スタッフ、実績などをしっかりとご覧いただいている。さて、このアクセスは仕事に発展するだろうか。 最近GyaOのCMをエンコードする仕事が増えてきた。メディアエンコーダーで簡単にエンコード出来るのにどうしてかと思っていたが、USENの仕様書は非常に厳格なもので、放送用の番組交換基準に近いものがある。映像やコンピューターに慣れていても難しいだろう。転送ビットレートだけではなく、映像、音声ともにコーデックが厳しく指定されている。配信サーバーの規格だけではなく、CMとしての品位も高くなるような数字だ。また、オーディオコーデックについてはより厳しい指定があり、普通のXP環境ではエンコード出来ない。そういえば最近BIGLOBEストリームがリニューアルし、配信画面がフルサイズになった。徐々にネット放送がテレビに近づいてきたようだ。そしてUSENの競合現るといったところか。 動画ファイルのエンコードにはメディアエンコーダー(↑上の写真)や リアルプロデューサー(↓下の写真) 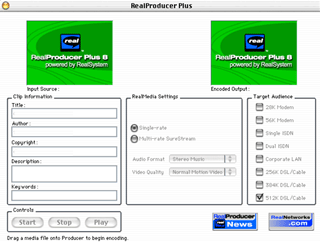 クイックタイム(下の写真↓)などを使用する。 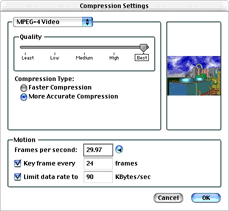 メディアエンコーダーを例にすると、転送ビットレートなどを細かく調整出来るようになっている。 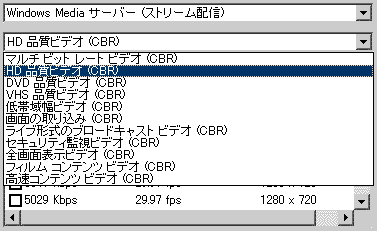 この設定は技術も大切だが、エンコード作業の経験による勘が大きく影響する。デジタル時代に勘とは可笑しな気がするが、画像の動きや色数、諧調などによって最適なエンコードを探らなければならない。 今回の検索に有った料金だが、これは持ち込まれるフォーマットによって変わるが、ちなみにDVで持ち込まれた5分未満の作業ではキャプチャー費5,000円とエンコード費5,000円、納品メディア費、そして消費税になる。急ぐ場合はサーバーにアップしての納品となる。 |
2006年04月03日(月)
|
HVR-Z1Jをキーワードにした検索が未だ落ちない。HVR-Z1Jのページも更新しないままなのでYahoo!やGoogleでは11件目で2ページ目になってしまったが、MSNではソニーに次いで2位となっていた。HDVへの関心度が高いためだろう、10件/日を割るのは日曜日くらいだ。 HVR-Z1Jを導入して2年目になるが、その稼働率は極めて高く、この小さなキャメラが大きな仕事をこなしてくれる。Z1J単独の1年間の売り上げはこのキャメラ十数台分に達している。小さく高性能であることを生かして特機を利用した撮影も多く、実際ミニジブやレールも使いやすい。ただしハンディーで撮影するにはどうも使いづらく、私の会社ではどちらかといえばEFPスタイルでの用途が多い。 ハンディーではZ1Jのように腕で支えるキャメラよりも肩乗せタイプの方が遥かに安定している。しかし肩乗せのハイビジョンとなるとHDCAMかDVCPRO-HDとなり、コストが大幅に上がる。予算が取れればHDCAMに越したことは無いが、予算あっての仕事である。趣味でキャメラを選ぶわけには行かない。 実は朗報が入ってきた。HDCAMとHDVの間を埋めるフォーマットとしてHDCAMの約半額でXDCAM-HDが発売されたのだ。XDCAM-HDの普及は局関係の導入状況にかかっている。  XDCAM-HDはHDVと同じMPEG-2 Long GOPだが、HD記録レートの選択が可能になった。HDVの25Mbpsよりも高画質なHQモード(可変ビットレート、上限値35Mbps)が選べる。XDDisc1枚でオーディオチャンネル数2ch時68分以上の記録が可能だ。 会社で導入したハイビジョン編集システムはHDV専用ではなく、100Mbpsのハイビジョン対応で、VARICAMやXDCAMに対応したものを選んでいる。ハイビジョンでの撮影オーダーが増えてきたため、現実的にXDCAM-HDの導入を視野に入れなければならない。 |
2006年04月02日(日)
|
HVR-Z1J HD 制作費である。 ハイビジョンの制作には様々なスタイルがある。すでにNHKの番組は殆どがハイビジョンで作られ、アナログ地上波のSDへはダウンコンバートして放送している。撮影キャメラはHDCAMが中心だが、最近ではソニーのHDVが使われだしている。特に水中映像ではHDCAM用のドラム缶並みのブリンプに比べ、HDV用は小型軽量化され、抜群の機動力である。HDCAMの画質を満点とすれば、HDVはCCDの画素やレンズの性能から70点というところか? MPEG2-TS(トランスポートストリーム)によるHDVフォーマットは本来保存用ファーマットで、編集フォーマットでは無いとされてきたが、その潜在能力には驚かされる。民生機用のMiniDVカセットに1125i(JVCは720p)のハイビジョンを1時間記録できるのである。そして画質もHD-SDIによりHDCAMへ変換しても十分に使用に耐えるものだ。 ハイビジョンの制作費においてはHDCAMの機材費に対してキャメラのみは1/3〜1/4で行える。ただしトータルの制作費はそうは行かない。撮影に必要な演出、キャメラマン、撮影助手、音声、照明のギャラ、機材費は抑えられない。これを削ると良い結果は生まれない。 驚くほどの潜在能力を秘めたHDVゆえに、私の会社もHDVに対応した編集システムを導入した。やはり仕事で使うためにはレンダリングせずにハイビジョンモニターでプレビュー出来ることが条件であり、デスクトップのオーバーレイだけでは無理がある。しかしHDVはバイオやiMacでも編集できるというのが売り物であり、外部モニターでのリアルタイムプレビューが必要無ければこういったシステムを組む必要はないだろう。  ↓編集ホストのHP社製ワークステーションとHVR-Z1J  ↓これはハードディスクとDVCPRO-HDのAJ-HD1200A DV端子での接続だが、HDVとは違い100Mbpsである。  いくら安くなったとは言え、業務用で使うためにはそれなりの設備投資が必要になる。ただし、HDVの編集がバイオやiMacでも出来てしまうから大変である。そして民生HDVのHC-1がヨドバシだけではなく、ケーズ電気でも10万円を切って売られていた。ウカウカしていると我々の立場が危うくなりそうだ。 |
2006年03月07日(火)
|
マンフロット505という検索だ。 マンフロットはイタリアのメーカーだがジッツォ等にもOEM供給している。ジッツォでは型番1380で売られているが、塗装やロゴが異なるだけで中身は同じだ。 スプリングが5種類付属し荷重は 1,2,5,8,10kg と対応できる。マンフロット505は残念ながらすでに生産完了し、入手は中古市場のみとなってしまった。 ビンテンのパーフェクトバランスと異なって、1,2,5,8,10kg のスプリングを交換することでキャメラの重量を打ち消すようになっている。若干不便なようだが、実はこのクラスのビデオ三脚の場合、ほぼ常用するキャメラは一定になるため、一度交換すればまず交換することはないだろう。私の会社ではビンテンがメインだが、小型のHDVキャメラHVR-Z1J用に505を2台使用している。HVR-Z1Jでは2kgのスプリングで完全バランスとなる。完全バランスとはキャメラの仰角にかかわらず止めた角度で静止することだ。この状態でフルードドラグを調整して粘りをつける。505の場合は上位機種の510よりも滑らかな動きをするため、私はビンテンと同等の評価をしている。 このクラスの国産品では残念ながら満足できるレベルには達していない。505が生産完了した今日、これに変わるものはビンテンのビジョン3になる。505とほぼ同等だ。上位機種はビジョン6になる。カウンター量もダイヤルで連続調整出来るワンランク上のクラスだ。価格も定価42万と数ランク上になる。非常にすぐれた505だが、マンフロットがビンテン傘下になったことを考えればビジョン3〜6を売るために505は邪魔だったのだろうか。あくまで憶測だが、そう考えてしまう。 なおマンフロット505でイメージ検索すると私の会社の写真のみが検索されていた。 |
2006年03月04日(土)
|
メディアエンコーダ 配信動画 保存である。 ストリーミングデータの保存にはけっこう苦労されているようだ。本来ストリーミングとはデータをパソコンに残さない配信方法ということで、著作権問題などを考えると無理なように思われる。しかし、実際には様々なアプリケーションがあり、動画であろうと、音楽であろうと、至って簡単に保存できてしまう。フリーソフトもあるようだが、私が使っているのはMPXやとりメロMP3である。ストリーミング中にWinAmpで再生も出来、かつ保存することが出来る。気に入っている放送局は「NetClassix-Rock from the 60s 70s」だ。192kbps〜256kbpsで配信されているので音質も文句なしである。 配信されているものはWho、Rolling Stones、Monkees、Guess Who、Doors、Beatles、Steppenwolf、Santana、Pink Floyd、Led Zeppelin、Jimi Hendrix、Janis Joplin、ClaptonにDerek And The Dominos等等、限りなく60s 70sだ。放っておけば一晩に数百曲は溜まってしまう。とりメロが優れている点はLaylaのように何度も放送される曲が重複して保存されないことだ。これはありがたい。そして動画も世界各国ニュースや映画、ドラマ、さらには猥褻番組まで、様々なものがある。そして保存したものはMediaPlayer、iTune、WinAmp等で再生できる。 大変便利なものだが、保存したものはあくまで自分で視聴するためであり、他人に渡したりWEBにアップしてはいけない。こういったソフトが合法なのか、違法なのかは定かではないが、これが違法なら市販されているビデオデッキや、HDレコーダーも違法になってしまうだろうから、問題はないのだろう。現にこういったソフトがインターナルから発売されている。 こういう作業をすると、昔FM放送をエアチェックした時代を思い出す。当時は2Trackの6mmテープを使用したが、レベルの設定や番組予約に苦労したものだ。それが今では放っておいてもデジタルデータで保存できてしまう。 MPXを使うとGyaOやその他様々なネット放送も保存できてしまうようだ。海外の放送局に「Jpopsuki tv!」というものがあり、500kbpsでJPOPのPVを放送している。私は見ないが、モーニング娘のPVも流していた。便利な機能としては、ネット放送をNTSC出力付きのビデオカードを使用することでテレビモニターで見ることが出来る点である。やはり放送はテレビモニターで見るに限る。 写真はWinAmpのスキンのひとつだが、デスクトップにシスコンが構築できるものである。レイアウトも自由だし、ウーハーが音に合わせて動いたり、イコライザーの入力レベルが調整できるなど、痒いところに手が届くスキンだ。もちろんフリーソフトである。 |
2006年02月25日(土)
|
HVR-Z1J 映像制作がキーワードだ。 HDVハイビジョンもかなり普及し、会社での稼働率も高くなっている。特に今後のハイビジョン利用を考え、SDの場合もHDVで撮影し、編集はダウンコンバートというスタイルも多い。近い将来ハイビジョンDVDの規格が決まり、安価な記録メディアと書き込みソフトが出回ればイベント映像の大半はハイビジョンに変わるだろう。それまでの暫定期間はやはりハードディスクメディアに依存するということになるが、編集においてHDVをMPEGで編集するのではクォリティーの低下は否めない。HDVだからこそ編集はAVIで行わなければならないだろう。何処と無く「高品位なVHS」を作るために「放送以上の編集クォリティー」を求められた時代を思い出してしまう。 |
2006年02月24日(金)
|
DSR-2000が発売されてから結構過ぎた。 報道資料によると発表は1999年3月19日で発売は99年10月である。私の会社では当初DSR-80を導入予定でしたが、ソニーのサービスマンに「80は文教用です。千里さんは買っちゃ駄目です。絶対にDSR-2000にしてください」と猛反対され、メーカーのサービスさんが言うんだからそれを信じて2000にした。80に比べて2000は50万高いわけだが、今思うと2000にしてよかったと思う。その後コストを抑えた1500なども発売されたが、未だDVCAMではDSR-2000Aが最上位機種にに君臨している。 2000と2000Aの違いはiLinkカードが付いた点だが、購入後すぐにiLinkカードを挿しているため、実質2000Aと同じスペックで今日も元気に動いている。下位機種に比べるとSDI入出力を装備し、DVCPROの再生も可能な上、民生DVのLPモードも再生可能だ。メカのレスポンスも良く、作業において全くストレスを感じない。 ベーターカムと並ぶ息の長いVTRは、結果としてコストを抑えることに役立つと言えるだろう。DSR-2000は使用頻度も多く、次回はCメンテでほぼすべてのメカが入れ替わる。 |
2006年02月20日(月)
|
キーワードは「ユーザーズビット」だった。 我々が使うVTRはタイムコードの記録及び設定が可能だ。そしてタイムコード(TC)の他にユーザーズビット(UB)の設定が出来る。特にUBはLTC(長手方向のトラックとは別に、映像信号にVITCとしてLTCとは別なデータを埋め込むことが出来る。通常LTCUBにはVTRのIDや24ロール以上(タイムコードでは24本以上管理できない)のロール管理用IDを入れたりする。一方VITCUBにはリアルタイムの時刻情報をFREERUNで記録する。 しかしUBでのロール管理は面倒くさいということで余り使いたくない。23本までのロール管理は01:00:00:00で始まるTCから23:00:00:00までのTCと使っているが、TCを24Hで繰り上がるように決めたには誰かは知らない。しかし我々の業界が24時間を超えて30時間制を使うようにTCもプリセットは99Hまで使えるようにしてもらいたい。当然SMPTEタイムコードだからSMPTE(米国映画テレビ 技術者協会)の規格があって、間単には変更できないだろう。だが、カウンターは10進も可能なはずだから、規格外であれば99HのTCは利用できるだろう。もしそうなれば非常に助かると思うのは私だけでは無いと思う。取材量が多くなればロール数はすぐに数十ロールになってしまう。999Hとはいわないが、せめて99Hまでは利用可能なTCを考えていただきたい。 |
2006年02月19日(日)
|
久しぶりの更新になる。HD作品の収録、編集などでWEBにアクセスしている時が無かった。今回のキーワードは「ダウンコンバート」だ。 以前はPCの画面をテレビ信号に変換することが主な用途だったが、今はハイビジョンを従来のスタンダードディフニション(SD)に変換することが主な用途になる。もちろんPC用途はハードウエアが異なるため、流用はできない。また、SDをHDに変換することはアップコンバートといい、当然アップコンバーターが必要になる。余談だが、J:COMのケーブルテレビチューナーにもHD→SDのダウンコンバーターが内蔵されていて、ハイビジョン放送を一般テレビで視聴出来るようになっている。ただし解像度はハイビジョンにはならない。 私の会社でダウンコンバーターを使用するのは、HD(1080iや720P)の収録テープをオンライン編集(本編集)を行う前にオフライン編集(仮編集)をするためだ。HD編集ではコストがかかるため、収録テープと同じタイムコードが入ったSDテープでAdobePremiereなどを使って16:9の仮編集を行う。完成した編集データをCMXフォーマットのEDLに書き出してオンライン編集を行う。仮編集で数十時間を費やし、そのデータをもとに数時間のオンライン編集を行うことで無駄なコストを抑えることができる。 現在ではHDV方式によるDTVもWIN、MACとも可能になったが、やはりHDCAMやVARICAMの画質には及ばないため、当分はオフライン編集は必要だ。しかしこれも数年後にはデスクトップで可能になるのではと期待している。 |
2006年02月04日(土)
|
「トラックイン ズームイン」がキーワードのアクセスだ。TR-INと省略するが、キャメラが移動して被写体に近づく撮影方法である。逆にTR-B(トラックバック)は被写体から離れる撮影方法で、ブログで言うトラックバックとは意味が違う。 トラックインに対してズームインという技法はレンズの焦点距離を可変できるズームレンズにより被写体を寄せることだ。逆はズームアウトになる。トラックイン、ズームインとも一見似たように思われがちだが、トラックインの場合は画角は変化せずに、キャメラの動きによって被写体の大きさが変化する。ズームインが凝視の効果があるのに対し、トラックインは人間の視覚に準じた効果が得られる。 映画ではレールやクレーンを使うことは常識だが、ビデオでは予算の制約からこういった特機の利用は限られてしまう。しかし私の会社ではHDV方式のハイビジョンキャメラを使用することで機材費を抑えて、浮いた予算で特機を使用することを勧めている。昔の業務用DVフォーマットに比べるとHDV方式のハイビジョンキャメラはダウンコンバートしても従来の業務用キャメラに匹敵する映像を記録できるようになった。機材費の抑制による画質低下も気にならないどころか、HDVのおかげで従来の予算ではなし得なかったキャメラワークが実現可能になった。 画面サイズがワイドになったことで、画面全体の情報量が増え、映画と同じ技法が必要になり、今後ますますレールやクレーンなどの需要が増えるのではないだろうか。 |
2006年01月28日(土)
 一青窈さんのライブを放送していたからだろうか、祇園甲部歌舞練場 映像制作会社というキーワードが有った。一青窈さんのライブは先日ラジオで聞いたが、昭和歌謡をとてもいい感じで唄っておられた。歌唱力もさることながら、彼女の人生観も魅力的だ。 一青窈さんのライブを放送していたからだろうか、祇園甲部歌舞練場 映像制作会社というキーワードが有った。一青窈さんのライブは先日ラジオで聞いたが、昭和歌謡をとてもいい感じで唄っておられた。歌唱力もさることながら、彼女の人生観も魅力的だ。祇園甲部歌舞練場は芸妓や舞妓の踊りの練習場として建てられたもので先斗町には先斗町歌舞練場がある。祇園甲部歌舞練場のすぐ傍らに八坂女紅場学園があるが、これは明治五年に創設された八坂女紅場が母体の舞妓・芸妓のための学校法人である。 以前祇園甲部歌舞練場で撮影したとき、小屋付さんの一人にMさんが居られて助かったことがある。はじめての小屋で知り合いがいるということほど心強いことはない。しかし何処かの小屋でヘマをして悪いうわさが流れるとこれほど怖いことも無い。幸いにも私の会社は今までにそういう経験は無いが、そんな目に合わされた会社を見ると真に気の毒だ。小屋では何よりも挨拶第一、安全第一である。 |
2006年01月14日(土)
|
ビンテンとはイギリスの三脚メーカーのことだ。 ビンテンと並ぶもう一つの三脚メーカーはサクラーだ。英国製とドイツ製で性格は全く違うが性能は同レベルで、いずれも業界トップレベルのものである。性格が異なるため、キャメラマンもビンテン派、サクラー派に大きく分かれる。ちなみに私はビンテン派になる。 三脚というとどうしても足の部分を思い浮かべるが、重要な部分はキャメラを保持するヘッドである。脚は頑丈で軽量なら特に問題は無い。タワミやネジレを起こさない剛性と、スピーディーな高さの調整が出来ればよい。 問題はヘッドである。約10kgのテレビキャメラをキャメラマンの意図通りに振るために様々な機構が備えられている。まずキャメラの重量を打ち消すためのカウンターバランス。キャメラを上下に振る(縦パン)場合に、回転の中心がキャメラの重心にないためにキャメラを止めたいところで止めることができずに重力によって引っ張られてしまう。ビンテンではカウンターバランスを連続可変させることで、キャメラの重量に対するカウンター量を最適に調整できる。メーカーではこれを完全バランスと呼んでいる。またサクラーも数種のカウンター値を組み合わせることでかなりいいバランスに調整できる。2者の違いは正確さをとるか、敏速さをとるかの違いだが、これは使い手の好みで評価が異なる。 カウンターバランスと同様に重要なことは動きの滑らかさである。ただ単に滑らかさを求めるのであれば、ベアリングを入れれば良いのだが、動く速度をコントロールすること、すなわちパンのスピードを自在に制御するためには様々な機構が必要となり、各社ともシリコングリス等による抵抗(フリュードドラッグ)を備えている。フリュード:Fluidとは流体のことで、ドラッグ:drag(釣りでは一般的にドラグ)とは抗力のことだ。ヘッドとはまさに流体力学の塊である。ヘッドは一定の力を加えた時、滑らかに動き出し、力を抜くと滑らかに止まること、かつ速いパンもゆっくりとしたパンもドラグ量の調整で速度を決められることが理想的なヘッドである。逆にそのようなヘッドであればドラグ量を一定にして、力の強さで速度をコントロールすることも容易に行える。 残念なことに国産ヘッドでは未だ完成域に達していないと思う。デモ機などで触ってみると、無負荷(キャメラが乗っていない状態)ならかなりいい動きをするようだが、いざ負荷がかかると歴然とした差を感じてしまう。このあたり、日本の精密加工技術を発揮してもらいたいものである。ただしビンテンやサクラーの場合は国産モデルの数倍の価格で、例えばビンテンのビジョン100では100万ほどになる。それでも我々キャメラマンがビンテンにこだわるのはその性能であり、キャメラワークとして残るからである。三脚のヘッドに限っては「弘法は筆を選ばす」は通用しない。 なお、大型の中継キャメラでは必ずといって良いほど国産メーカーの昭特に軍配が上がる。ビンテンのベクターシリーズよりも昭特を好むキャメラマンは非常に多い。余談だがビンテン傘下になったイタリアのマンフロット社では三脚〜ヘッドのことをキャメラサポートと言っている。私はこの言い方が好きだ。 ※本文中でサクラーと書いているが、SACHTLERをザハトラーと読む人が多くなった。そしてこの読み方が正しいのはオフィシャルであるSACHTLER JAPAN CORPがザハトラー・ジャパンと書いていることで明らかだが、なぜか業界OB達はサクラーと呼び続けている。もちろん私もサクラーと呼ぶが「赤信号、みんなで渡れば怖くない」といったところだろうか。  |
2006年01月12日(木)
|
ストリーミング 技術会社 大阪ではけっこうアクセスがある。ブロードバンドの普及で今年はインターネット放送事業が定着する年になりそうだ。 以前にも私はビグローブの動画配信サイトでニュースを見ていると書いたが、USENが運営するパソコンテレビ GyaO [ギャオ]は注目のネット放送局だ。 「USENが運営するGyaO!全番組が完全無料のパソコンで見るテレビ!人気の韓国ドラマから最新ニュース、さらには映画のオンライン試写会など見逃せない番組、新作が毎日続々と登場します!」ということだが、確かに凄い。CM収入で運営し、USENブロードバンドのユーザー以外も自由に利用できる。必要なのはメールの登録だけだ。 メールを登録すると後に様々な広告メールや迷惑メールが増えるので心配だが、説明では心配はないようだ。念のため私はこういう用途専用のアドレスを使って登録した。 一度登録するとクッキーを使って次回からのログイン手続きは不要になり、ワンクリックで映画やドラマ、PVがたっぷり堪能できる。そしてネット放送の一番の強みであるオンデマンド放送は何よりの魅力だ。日本にファンの多い韓流ドラマの「冬ソナ」も1時間15分たっぷり見ることが出来る。今は18話を放送中だ。他にも様々なコンテンツがあり、いくつかのプログラムは我々のビジネス対象となっているし、今後も大きな需要が期待できる分野になるだろう。 ネット放送といっても昔と違いビットレートも高く、画像、音声ともテレビに近づいている。今後はハイビジョンも視野に入れた展開も期待できるだろう。技術会社としてはTV放送もネット放送も同レベルで制作しなければならない時代が来た。 |
| 前へ | 次へ |
PHOTOHITOブログパーツ
|
ニックネーム:SENRI 都道府県:関西・大阪府 映像制作/撮影技術会社 (株)千里ビデオサービス 代表取締役& 北八ヶ岳麦草ヒュッテHPの管理人です。よろしくお願いします。 ↓色々出ます↓ »くわしく見る バイオグラフィー |